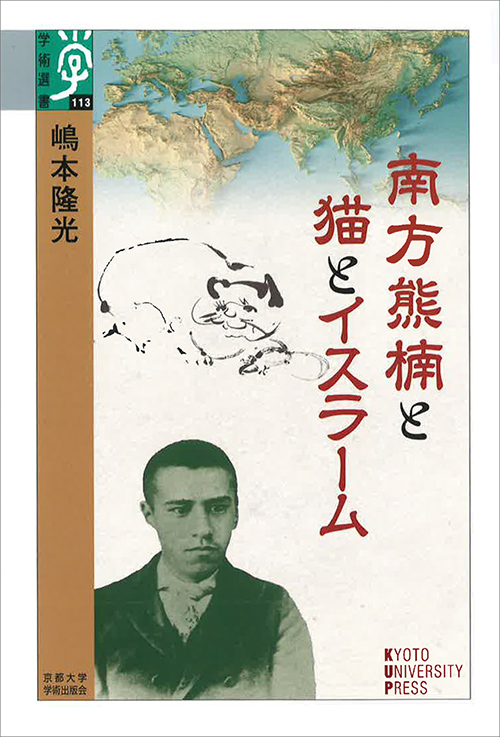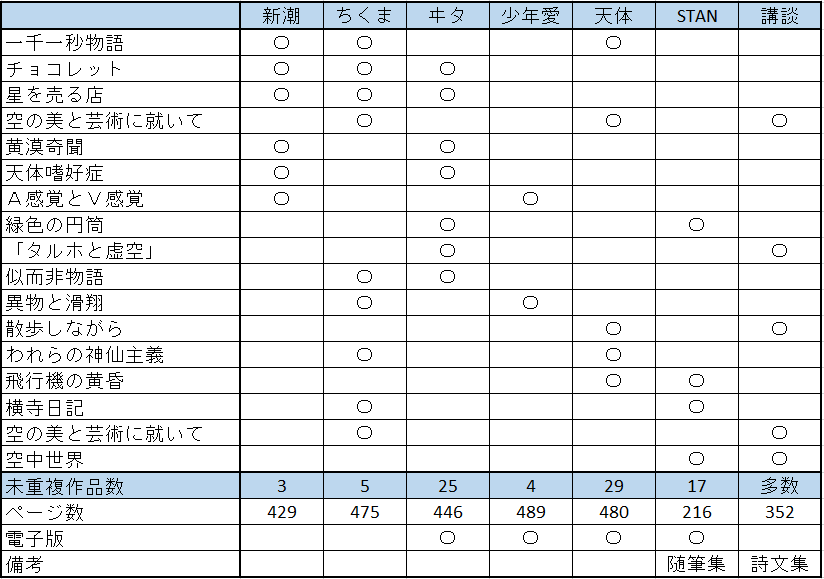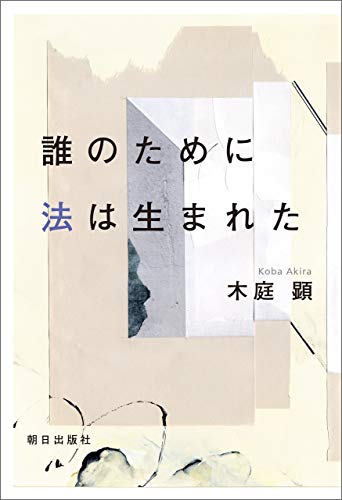あけましておめでとうございます。年が明けて当ブログもいよいよ3年目に突入したわけですが、一体いつまで続けるつもりなのでしょうか。誰に頼まれたわけでもない更新ですが、自分が楽しんでいるうちは続けていこうかと思います。一番読んでいるのが自分という気もしますが……
それでは昨年12月に出た気になる本です。
吸血鬼小説の古典と名高い「カーミラ」を含む、19世紀アイルランドの作家レ・ファニュの新訳作品集。訳者はチェスタトン、ラヴクラフトを始め多くの訳書と、小説や評論・エッセイなども多数刊行している。
内容説明が最高なのでそのままコピペしますが「18世紀ロンドンで建設中の七つの教会に異端建築家が仕掛けた企みと現代の少年連続殺人の謎。過去と現在が交錯する都市迷宮小説。」1997年新潮社刊の単行本が白水uブックス入り。作者は伝記作家としても知られているそうで、近訳書に『シェイクスピア伝』など。訳者はキング作品や国書刊行会版のラヴクラフト全集など訳書多数。
カナダの異色作家による奇想ミステリが文庫化(単行本は国書刊行会2011年)。訳者は『パラダイス・モーテル』など同作者の他作品やJ.G.バラードなども手がける。
作家であり中国語小説の翻訳家でもある立原透耶(『三体』の監修も務める)による中華SFのアンソロジー。
ボルヘス最後の短編集が岩波文庫より。エッセイや評論ではなく小説のようです。おなじみ鼓直のほか、『ケンジントン公園』の訳書がある内田兆史が訳者に名を連ねる。
これが初邦訳となるアメリカ人作家による、LAを舞台にした女性二人のラブストーリー。訳者は他に『聖なる証』などエマ・ドナヒューや絵本リトルブルー・シリーズなどを手がける。
アガサ・クリスティ賞の大賞受賞デビュー作。1936年の仏領インドシナへ留学した女子学生が主人公の歴史ロマンとのこと。
『ソフィストとは誰か? 』でサントリー学芸賞を受賞している著者による、プラトン『国家』読解。2011年の単行本が文庫化。『西洋哲学の根源』『ギリシア哲学史』『対話の技法』など近著多数。『ソクラテスの弁明』など古典新訳文庫でプラトンの新訳も。
19世紀以降のヨーロッパで声高に語られ始めたセクシュアリティが、いかにナショナリズムと結びついたか。著者はドイツ社会史が専門で、他に『英霊 ――世界大戦の記憶の再構築』『大衆の国民化 ――ナチズムに至る政治シンボルと大衆文化』の邦訳あり。訳者はメディア論が専門で近著に『メディア論の名著30』『池崎忠孝の明暗: 教養主義者の大衆政治 近代日本メディア議員列伝』『『キング』の時代――国民大衆雑誌の公共性』など。
パンデミック以降に書かれた、ジュディス・バトラーの2022年の著書がさっそく邦訳。『非暴力の力』『問題=物質となる身体 「セックス」の言説的境界について』『[新版]権力の心的な生』など近訳書も多数。訳者は他にジジェク、ド・マンなど手掛け、著書に『ジョイスの反美学: モダニズム批判としての『ユリシーズ』』など。
近年なかなか見ない、古典的な意味での直球の映画批評の本。著者は2019年に『評伝ジャン・ユスターシュ: 映画は人生のように』を刊行している。
2009年に講談社現代新書から出ていた日本の現代思想・批評ガイドの定番書が増補新版で文庫化。
『逝きし世の面影』などで知られる歴史家の2013年の講義録が新版で平凡社ライブラリー入り。最近は他にも『黒船前夜(新装版) ロシア・アイヌ・日本の三国志』『《新装版》江戸という幻景』など新版がいろいろが出ている。
謎めいたタイトルだが、ロンドンにおける熊楠の研究を批判的に検証した本のようだ。著者は『イスラームの神秘主義: ハーフェズの智慧』『イスラーム革命の精神』などの著書のあるイスラーム現代思想の専門家。
1966年に発表された、網野善彦の原点となる研究が岩波文庫で復刊。近著もいろいろあるようですがやっぱり定番は『異形の王権』『無縁・公界・楽』あたりかと。
アメリカの日本学者による、伊勢神宮の本格的研究。著書は他に『東京ヴァナキュラー:モニュメントなき都市の歴史と記憶』『帝国日本の生活空間』など。
米・独・カナダの著者による、移民研究の基本書が文庫オリジナルで登場。原著2009年。訳者は他にホブズボーム『20世紀の歴史 上 』『下』などを手がける。
邦訳書も多い建築史家による、本格的なモダニズムの建築家ガイド。他の邦訳書に『近代建築の歴史 1851-1945』『現代建築入門』『ミース再考 その今日的意味』など。訳者は他にも『世界を変えた建築構造の物語』など建築関連書を多く翻訳している。
音楽と小説に関する本の多い著者による、漫画や映画も含めたディストピア作品批評。近著に『ディストピア・フィクション論: 悪夢の現実と対峙する想像力』『意味も知らずにプログレを語るなかれ』『戦後サブカル年代記』など。
2021年に『日本の〈メロドラマ〉映画──撮影所時代のジャンルと作品』でデビューした映画研究者による、さらなるメロドラマ映画研究。
SNSによって言語を取り巻く状況はいかに変化したかを多角的に論じる。音楽家でもある著者の近著には『歌というフィクション』『平成日本の音楽の教科書』『平岡正明論』などがある。
ではまた来月。