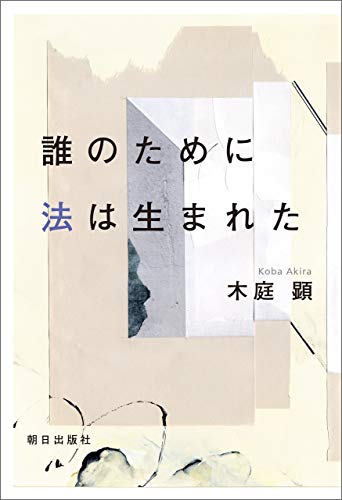法学の立場から国家の役割を問う新書
私たちはふだん法律に従って生活しているが、ではその法律、あるいは法律を執行する国家が「正統なもの」であると、どのように納得しているだろうか?
いざこのように問われると、答えに詰まってしまう方も多いのではないだろうか。今回紹介する嘉戸一将『法の近代 権力と暴力をわかつもの』は、法学の立場からその問題の系譜を見ていく本だ。
本書では、先の問題は簡潔なフレーズに言い換えられる。いわく、「権力と暴力を区別するものは何か?」。あるいは、「何が国家と盗賊を区別するのか?」。
「法」の起源 主権とキリスト教
現在の社会において法律を作るのは立法機関だが、それに応じてこの問題を言い換えれば、「私たちは立法機関を通じて、意のままに法を創ることができるのか?」となる。議会制民主主義であれば選挙によって選ばれた代表者が法律を作るわけだが、果たして彼らは「意のままに」法律を作ってもよいのだろうか? 「意のままに」創られた法律は、果たして正統性を持つのだろうか? 立法において、何かしらの権威のようなものに従う必要はないのか?
ここで「主権」という概念が登場する。「主権者」とはつまり立法者のことであり、ひとまずは、この「主権」が立法の正統性を保証すると言われる。
この概念は17世紀頃の西欧において、宗教戦争(三十年戦争)の惨禍の中から法秩序を打ち立てるために考え出されたものだ。主権=正統性を持つ君主などが法を作り、国民はそれに従うべしという観念によって、社会の混乱を収めて秩序をもたらそうとしたのだ。
私たち日本人も、明治憲法における「天皇主権」から日本国憲法の「国民主権」への変化、という形でこの言葉に馴染んでいるだろう。
では、この「主権」とはもともとどういう意味の言葉なのか。
そもそも、主権(sovereignity)という観念そのものが、一神教の神の絶対的な高さ、すなわち至高性(sovereignity)に由来している。
(「序章 法と近代」より)
「権力と暴力を区別するものは何か?」「何が国家と盗賊を区別するのか?」という問いへの、ひとまずの答えがこの「主権」という観念なのだが、その権威は神によって保証されるものだったのだ。
本書ではまず、法学についての歴史的な前提が確認される。
すなわち、いま私たちが「法」と呼んでいるシステム自体が、もとはと言えば中世ヨーロッパにおいて古代のローマ法が「再発見」され、それが社会の規範として適用すべく研究・解釈されてきたことに由来する、という事実である。つまり、私たちが普遍的なものだと思っている法のシステムは、実は西欧というローカルな社会が、古代の法律の研究を通して生み出した概念なのだ。そう考えると、法の正統性という観念そのものが神と結びついていても不思議はない。
とはいえ、歴史が下るにつれて西洋社会も世俗化が進み、主権の捉え方も変化していく。本書はこの主権についての歴史的な議論を詳細に見ていくことになる。
シュミットとケルゼンの対立
ここで軸となるのがカール・シュミットとハンス・ケルゼンという、二十世紀前半に活躍した二人の法学者の対立だ。
シュミットは「主権者とは非常事態についての決断者である」、つまり戦争などの非常事態において決断を下す者こそが主権者なのだというテーゼで有名だが、彼は神の権威が弱まった世俗化の時代において、国家の代表として決断を行う者が必要だとした(「決断主義」)。シュミットは経済的な効率や各勢力の利害関係によって支配されるようになった議会制を批判し、本来の民主主義の実現のためには、国民の支持を得た強力な決断者が必要だとする。そしてこの決断者は単なる独裁者ではなく、国民の意思を代弁するものでなければならない。
ここまで読んで、いや、それはちょっと危険なのではないか?と思う人も多いだろう(事実シュミットはナチス・ドイツに加担したことでも知られる)。このシュミットの主張を批判するのがもう一方のケルゼンだ。ケルゼンは、シュミットの主張は「信仰」を前提としていると批判する。シュミットの言うことを信じるには、決断者が国民の意思を代弁するということを信じなくてはならない。それはケルゼンから見れば「神的な権力への帰服」である。
それに対してケルゼンが主張するのは、価値の中立性、徹底的な相対主義だ。ケルゼンは法の成立する根拠を「根本規範」、すなわち共同体によって認められる規範にあるとする。皆にとって納得のできる法が正統な法というわけだ。
このように言われると、どうしてもケルゼンの言うことの方が穏当なように思えるのだが、しかしここで著者は「両者の間に横たわる問題はいまだ解決されていない」と注意を促す。
ケルゼンのいう根本規範は、「法が生産される」という近代固有の観念を反映しているという。しかし、果たして法とは、人々の意のままに作られても良いものなのだろうか?
著者によれば、ケルゼンの立場は「正義の観念を法の領域から排除する」ものだという。法は正統性を必要とするが、果たしてその正統性は、「みんな」によって担保されうるのか。そこには何か、かつてヨーロッパで「主権=至高性」と名付けられたような権威と、それに対する信が必要なのではないのか。一体何が、「正義」をなすものなのか。
本書が歴史上の議論を詳細に追いながら考えるのは、このような困難な問いである。そして著者によれば、「法学」においてこのような問いについて考えるには、歴史を紐解く以外に方法はないという。
西ヨーロッパが古代ローマの市民社会に模範とすべき文明を見出し、その規範を受容したのが法の探求、すなわち法学の始まりである。それが、人の意のままになるものを指すのではないことは言うまでもない。人間にとって規範となるものの理念を歴史に絶えず問い直すことが、法を探求することなのである。
私たちが、国家という制度(その形態がどのようなものであれ)のなかで生き、法秩序を刷新し続ける(議会制か独裁制か、その方法がどのようなものであれ)限り、そして法が意のままには創られない限り、繰り返し論じられてきたものを検討することが必要だ。というのも、人間が別の何ものかに変身するのでもない限り、制度は人間的生の条件をめぐる、そして権力と暴力をめぐる、繰り返されてきた歴史からしか産み出されないからだ。
(同上)
日本にとっての「主権」と「自由な主体」
さて、ここまでは西洋における法と主権の問題について見てきたが、もし主権というものがもともとキリスト教と深く結びついた観念だったとしたら、西洋以外の国々ではそれはどのように捉えられるのか?
まさにその部分に、西洋の後を追って「国家」のシステムを導入した非西洋諸国のもつ問題がある。本書は、日本においてそれがどのような道を辿ったかについても詳細に見ていくことになる。
日本の近代国家化を担うべくヨーロッパを見聞した明治期の日本人たちは、そこに国家の基軸としていまだ根付いているキリスト教を見出し、日本においてそれに代わるものを必要とした。そして、そのために創出されたのが天皇信仰だという。
近代日本においては、キリスト教的な至高性の代わりに、天皇の権威が法の正統性を保障するのだ。そしてここには、西洋において主権国家の前提となっている「自由な主体」という観念そのものが存在しない。国民は飽くまでも「臣民」として、天皇のもとでの一体性のうちでのみ権利が保障される存在なのである。
本書によれば西洋は凄惨な宗教戦争の混乱を経ることで「信教の自由をもつ主体」という観念を生み出し、それを社会の基盤とした(それは「信仰の断念を自由という価値に転換した」と説明されている)。そしてそのような伝統を持たない日本では、そもそも「自由な主体」という観念が定着していないという。
そしてまた著者によれば、日本には「自由な主体」が存在しないがゆえに、自由に振る舞う強権的な支配者もまた存在しえないという。それゆえ日本ではシュミットが主張したような「決断主義」が採用されることはなかった。
しかし、この「自由な主体が存在しないがゆえに強権的な支配者もいない」という状況は、結果として「誰も決断しない」という体制をもたらすことになる。著者はパンデミックにおける「緊急事態」の状況を指して述べる。
しかし、実際には、強権的な支配が存在しえないにもかからわず、決断主義の挫折の裏面のようにして誰もが責任を引き受けることを逃れ、「協力」や「自粛」を「要請」する無責任な抑圧的言説が跋扈しているために、人間的生の保障は宙づりにされている。
(同上)
「人間的生の保障」、それを著者は国家の役割だと説明する。
それをもたらすことができるのは、正義の決断を行う主権者なのか。あるいは価値相対性の中で求められた規範なのか。シュミットとケルゼンの対立である。
「人間的生の保障」を実現するためにこそ、秩序をもたらす法の正統性はどこにあるのか、人は「意のままに」法を作っても良いのか、ということが問われている。それは抽象的な議論にも見えるが、私たちが日々目にしている状況は、どうやらこの問題と深く関わっているようだ。
国家の存立を支えてきたものが、何であるか、問われなければならない。より正確に言えば、権力を暴力と厳格に峻別することで、人間が人間としての生を享受することを保障するのが、国家の役割とするならば、その役割のために必要なものが問われなければならない。さもなければ、国家は人間なき国家に堕すことになるだろう。
(同上)
私は法学については素人ということもあり、本書の議論はとても刺激的なものであった。
これから他の本も読んでいきたい。
次の一冊
過去記事より、同じく主権をテーマにしながら、こちらは政治哲学の視点から語られた本。同じようなテーマでも、「法」と「政治」、あるいは「法」と「哲学」という切り口で内容が全く違うので面白い。
そのうち読みたい
今回の記事で紹介した『法の近代』著者の前著であり、同テーマをより詳細に論じた本だろう。
法学者による入門書で、紀伊國屋じんぶん大賞も獲っている本。中高生との対話をまとめたものなので読みやすそう。