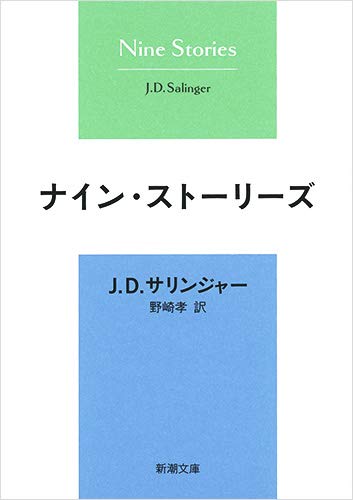ボルヘスの小説はこの文庫を買えばOK
- ボルヘスの小説はこの文庫を買えばOK
- ①代表的作品集『伝奇集』/『アレフ』
- ②比較的読みやすい『砂の本』
- ③異色作(でも小説としてはむしろオーソドックスな)『ブロディーの報告書』
- ④「ボルヘス最後の短編集」『シェイクスピアの記憶』
- ※実録評伝小説『汚辱の世界史』
- 小説以外の個人的お勧め本
- ※宣伝
ホルヘ・ルイス・ボルヘスを読んだことがなくても、名前を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。1899年、アルゼンチン生まれの作家。南米文学の巨匠、幻想と迷宮の作家、博覧強記の図書館長、長編をひとつも書かなかった小説家……その不思議で伝説的なイメージを語る言葉は多いです。
あるいは、かの有名な「バベルの図書館」の作者としてご存じの方も多いかもしれません。「バベルの図書館」とは、この世のあらゆる書物を収めるという幻想の図書館を書いた短編小説です。
世界文学、幻想文学、あるいはSFのファンの中にも愛読者が多いボルヘスは、私にとっても最も好きな作家の一人なのですが、今回はその代表的な小説が収録されている文庫を紹介しようと思います。というのも、ボルヘスは日本でも長く人気のある作家なので、日本語での刊行点数も非常に多く、しかも詩集やエッセイ、評論や講演集などもたくさん出ていくため、ちょっと読んでみようかなと思ってもどれが代表作なのか、それ以前にどれが小説なのかすらわかりづらいのです。
というわけで、今回は文庫で出ているボルヘスの小説集を、勝手ながら私のお勧め順に紹介したいと思います。
といっても、なにせボルヘスは一篇たりとも長編小説を書かなかった作家ですので、その量は少ないです。手に入りやすいものに関してざっくり言いますと、基本的に4冊しかありません。
(追記:2023年12月に短編集『シェイクスピアの記憶』が岩波文庫より刊行されたので追加しました。)
①代表的作品集『伝奇集』/『アレフ』
ボルヘスの代表作と言えば、やっぱりこの『伝奇集』。無限の図書館を書いた前述の「バベルの図書館」、庭園に作られた迷宮が登場するサスペンス「八岐の園」、架空の小説を評する形式の「アル・ムターシムを求めて」及び「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」、全ての出来事を記憶する男を書いた「記憶の人、フネス」など、技巧と幻想に満ちた代表的短編を読むことができます。暗号によって示された連続殺人事件を追うアンチ・ミステリ「死とコンパス」が好きです。鼓直訳。
収録作:
トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス/アル・ムターシムを求めて/『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール/円環の廃墟/バビロニアのくじ/ハーバート・クエインの作品の検討/バベルの図書館/八岐の園/記憶の人、フネス/刀の形/裏切り者と英雄のテーマ/死とコンパス/隠れた奇跡/ユダについての三つの解釈/結末/フェニックス宗/南部
1993年 原著1944年
追記:こちらの記事で『伝奇集』の内容を紹介しました!
『伝奇集』とどっちが好きか迷ってしまうもうひとつの代表作がこの『アレフ』。この短編集には、迷宮に住むミノタウロスの視点で書かれた「アステリオーンの家」、砂漠に作られた迷宮の秘密にまつわる「アベンハカン・エル・ボハリー、おのが迷宮に死す。」「二人の王と二つの迷宮」の連作など、「迷宮の作家」ボルヘスの迷宮小説がたっぷり味わえます。他にもホメロスの時代から生き続ける男の手記「不死の人」や、宇宙全体を含む小さな物体が登場する「アレフ」など、これぞボルヘスという短編がたくさん。こちらも鼓直訳。
なお白水uブックスから出ていた『不死の人』、平凡社ライブラリーから出ていた『エル・アレフ』と同じ本です。
収録作:
不死の人/死人/神学者たち/戦士と囚われの女の物語/タデオ・イシドロ・クルスの生涯(一八二九 ― 一八七四)/エンマ・ツンツ/アステリオーンの家/もう一つの死/ドイツ鎮魂曲/アヴェロエスの探求/ザーヒル/神の書跡/アベンハカン・エル・ボハリー、おのが迷宮に死す。/二人の王と二つの迷宮/待ち受け/門口の男/アレフ/エピローグ
2017年 原著1949年
②比較的読みやすい『砂の本』
この『砂の本』は、ボルヘスの作品集の中では比較的後期に書かれたもの。実験的な作風の小説も多い上記二冊と比べると、普通の小説っぽい形式の作品が多い気がするので、できるだけ読みやすいものから入りたい方はこれから読むのがいいと思います。篠田一士訳。
読みやすいとはいえ、冒頭の「他者」は過去と未来の自分が出会って会話する話、表題作「砂の本」は始まりも終わりもない謎の書物に関する話ですので、ボルヘスならではの幻想は十分に味わえます。秘密結社での日々を回想する、ちょっと青春ぽい雰囲気もある「会議」が好きです。
併録されている「汚辱の世界史」はボルヘスが初めて発表した小説集で、これは悪名高い実在の人物たちの評伝の形をとっています。なんと吉良上野介も登場。「ばら色の街角の男」は、ボルヘスの故国アルゼンチンに生きた「ガウチョ」と呼ばれるならず者たちを描いた小説です。
収録作:
「砂の本」
他者/ウルリーケ/会議/人智の思い及ばぬこと/三十派/恵みの夜/鏡と仮面/ウンドル/疲れた男のユートピア/贈賄/アベリーノ・アレドンド/円盤/砂の本
「汚辱の世界史」
ラザラス・モレル/トム・カストロ/鄭夫人/モンク・イーストマン/ビル・ハリガン/吉良上野介/メルヴのハキム/ばら色の街角の男/死後の神学者/彫像の間/夢を見た二人の男/お預けをくった魔術師/インクの鏡
2011年新版 『砂の本』(原著1975)と『汚辱の世界史』(原著1935)の合本
③異色作(でも小説としてはむしろオーソドックスな)『ブロディーの報告書』
この『ブロディーの報告書』はボルヘスの小説集の中では異色作。「鬼面ひとを脅すバロック的なスタイルは捨て...やっと自分の声を見いだした」と自分で言っているらしいのですが、その言葉の通り、ストレートな形式で語られた、実録・ドキュメンタリー的な短編が集まっています。多くの作品が、上記の「ばら色の街角の男」のような、アルゼンチンのガウチョたちの文化や生き様を書いており、ボルヘスが生きた世界の原風景を見るかのようです。アルゼンチンタンゴが聞こえてきそうな一冊。鼓直訳。
以前は白水uブックスから出てました。
収録作:
じゃま者/卑劣な男/ロセンド・フアレスの物語/めぐり合い/フアン・ムラーニャ/老夫人/争い/別の争い/グアヤキル/マルコ福音書/ブロディーの報告書
2012年 原著1970年
④「ボルヘス最後の短編集」『シェイクスピアの記憶』
2023年12月に岩波文庫から刊行。表題作はこれが初訳だそうです。逝去の3年前に刊行された短編集。
収録作:
シェイクスピアの記憶 一九八三年八月二十五日 青い虎 パラケルススの薔薇
2023年 原著1983年
※実録評伝小説『汚辱の世界史』
こちらは集英社文庫『砂の本』に収録されている『汚辱の世界史』が単体で刊行されたものですが、「マホメットの代役」「寛大な敵」「学問の厳密さについて」の三篇が追加されています。中村健二訳。
収録作:
ラザラス・モレル―恐ろしい救世主 トム・カストロ―詐欺師らしくない詐欺師 鄭夫人―女海賊 モンク・イーストマン―無法請負人 ビル・ハリガン―動機なき殺人者 吉良上野介―傲慢な式部官長 メルヴのハキム―仮面をかぶった染物屋 薔薇色の街角の男 死後の神学者 彫像の間 夢を見た二人の男 待たされた魔術師 インクの鏡 マホメットの代役 寛大な敵 学問の厳密さについて
2012年 原著1935年
小説以外の個人的お勧め本
今回の記事は飽くまでボルヘスの小説を紹介するものですが、ボルヘスには小説以外の本もたくさんあるので、ここではほんの一部を紹介します。
これは原著が1960年に刊行されたボルヘスの詩文集。詩と短い散文、そしてごく短い小説が収録されています。もちろん詩もとても良いのですが、私はこの、2~3ページで終わってしまうボルヘスの短い小説とも散文ともつかない文章が特に好きで、「王宮の寓話」「ボルヘスとわたし」「Everything and nothing――全と無」など何度も読み返してしまいます。鼓直訳。
これはボルヘスが収集した、古今東西の幻獣、怪物、空想上の生き物に関する記述を集めた本です。圧倒的な知識を操るボルヘスの面目躍如たる本で、その出典はものすごく多岐に渡ります。ケンタウロスやエルフ、あるいは八岐大蛇といったおなじみの名前から、「カフカの想像した動物」や、「釈迦の誕生を予言した象」などの気になる存在、そして数多くの全く聞いたことのない幻獣が計120種網羅されています。ダンサーでもあるマルゲリータ・ゲレロとの共著。柳瀬尚紀訳。
なお、こちらは今年のお正月に、寅年を祝ってボルヘスの「Dreamtigers──夢の虎」(『創造者』所収)を紹介した記事です。合わせてご覧ください。
※宣伝
2023年9月に開催された「第三回かぐやSFコンテスト」に投稿した短編SF小説が、選外佳作に選ばれました。近未来のパリを舞台としたクィア・スポーツSFです。